私たちは子どものころから、多くの時間をかけて「学ぶ」ことに取り組んできました。小学校では読み書きそろばん、中学校では理科や社会、高校ではさらに専門的な内容を学び、大学では自分の興味のある分野を深く掘り下げていきます。いわば、20歳前後までの人生は「インプット」の時間です。スポンジが水を吸い込むように、私たちは知識や経験、技術、価値観など、あらゆるものを体の中に取り込んでいきます。
けれども、ここで大切なのは、「インプットしただけでは終わりではない」ということです。知識は貯め込むだけでは意味がありません。それを社会に出て「どう使うか」、つまり「アウトプットすること」が本当の学びの完成なのです。例えるなら、料理のレシピをいくら頭に入れても、実際に台所に立って料理をしなければ、誰かにその味を届けることはできないのと同じです。
そして、この「アウトプットの力」において、現代を生きる私たちが避けて通れないのが「パソコンスキル」なのです。
たとえば、あなたが営業職に就いたとします。かつては「足で稼ぐ営業」と言われ、毎日訪問して関係性を築くことが重要でした。しかし今では、効率よく顧客の情報を管理し、過去のデータからニーズを予測し、効果的な提案をする力が求められています。これを手作業のノートや記憶に頼って行うのと、パソコンでデータベースや表計算ソフトを使って処理するのとでは、仕事のスピードも正確さもまったく違います。
これは例えるなら、地図を持たずに山を登る登山と、GPSと最新の地図アプリを使って登る登山ほどの差があります。知識や経験をアウトプットするための「道具」が整っていなければ、どれだけ努力しても遠回りになってしまうのです。
また、クリエイティブな分野ではどうでしょうか。音楽を作る人、イラストを描く人、小説を書く人――いずれも、作品を世に出すには「発信の手段」が必要です。今はSNSや動画プラットフォームの普及によって、個人でも簡単に作品を届けられる時代になりました。しかしその一方で、動画編集ソフト、音声編集ツール、画像加工アプリなどを使いこなせなければ、魅力的な形に仕上げることが難しくなっているのも事実です。
たとえば、同じメロディでも、ただスマートフォンで録音しただけの音源と、音質を整え、動画に編集し、視覚的にも魅せる形で発信された作品とでは、受け取る側の印象がまるで違います。それは、歌を録音しただけの「素うどん」と、丁寧に盛り付けられ、薬味が添えられた「フルコースのうどん」くらいの差があるのです。
さらに、パソコンスキルはアートや営業の世界に限らず、あらゆる職種に広がっています。たとえば、保育士や介護職といった人と向き合う職業でさえ、報告書や記録をパソコンで作成する場面が増えています。フリーランスや個人事業主で働く人も、請求書や企画書、宣伝資料の作成、オンラインミーティングなど、パソコンが使えるかどうかで仕事の質が大きく変わってきます。
極端な言い方かもしれませんが、現代は「パソコンという道具を使ってアウトプットできる人」と「それができない人」とで、人生の選択肢に明確な差がつく時代です。たとえ話をするなら、絵の具を持っているけれど筆がない画家、どれだけ優れた楽譜を書いてもピアノが弾けない作曲家――そんな状況に近いのかもしれません。
そしてもうひとつ大事なのは、パソコンが得意というだけで「選ばれる」ケースが非常に多くなっていることです。実際に私の知人で、会社内で突然「資料づくりを任されるようになった」と言う人がいました。彼はこれまでまったく目立たない存在でしたが、パワーポイントが得意だったことから社内プレゼン資料の担当になり、そこからどんどん評価されていきました。「やれる人が少ないスキル」を持っているだけで、一気に注目されることがあるのです。
つまり、パソコンスキルとは「知識や経験を見える形に変える力」であり、「誰かに伝える力」でもあります。インプットしてきたものを最大限活かすための、現代における“必須の言語”だと言えるでしょう。
もちろん、全員がプログラマーのように高度な技術を身につける必要はありません。でも、自分の思いや知識を形にして届けるために、基本的な操作や表現方法は、誰もが学ぶべき時代になっています。
「勉強したのに、うまく伝わらない」「才能はあるのに、評価されない」。そんな風に感じている人こそ、自分の中にあるものを“アウトプットする技術”を見直してみてほしいのです。
これからの時代、「学ぶ力」だけでなく、「伝える力」「届ける力」こそが本当の武器になります。そして、その力を支えるのが、パソコンという道具です。だからこそ、今、若い世代に伝えたいのは、「自分の可能性を形にしていくには、パソコンという武器を持っておくことが必要だよ」というシンプルなメッセージなのです。
そして、若い世代だけではなく、今50代以下でパソコンスキルの必要性を感じている人がいたら、苦手意識を持たずにパソコンを使いこなせるように取り組んでいただきたいと思います。
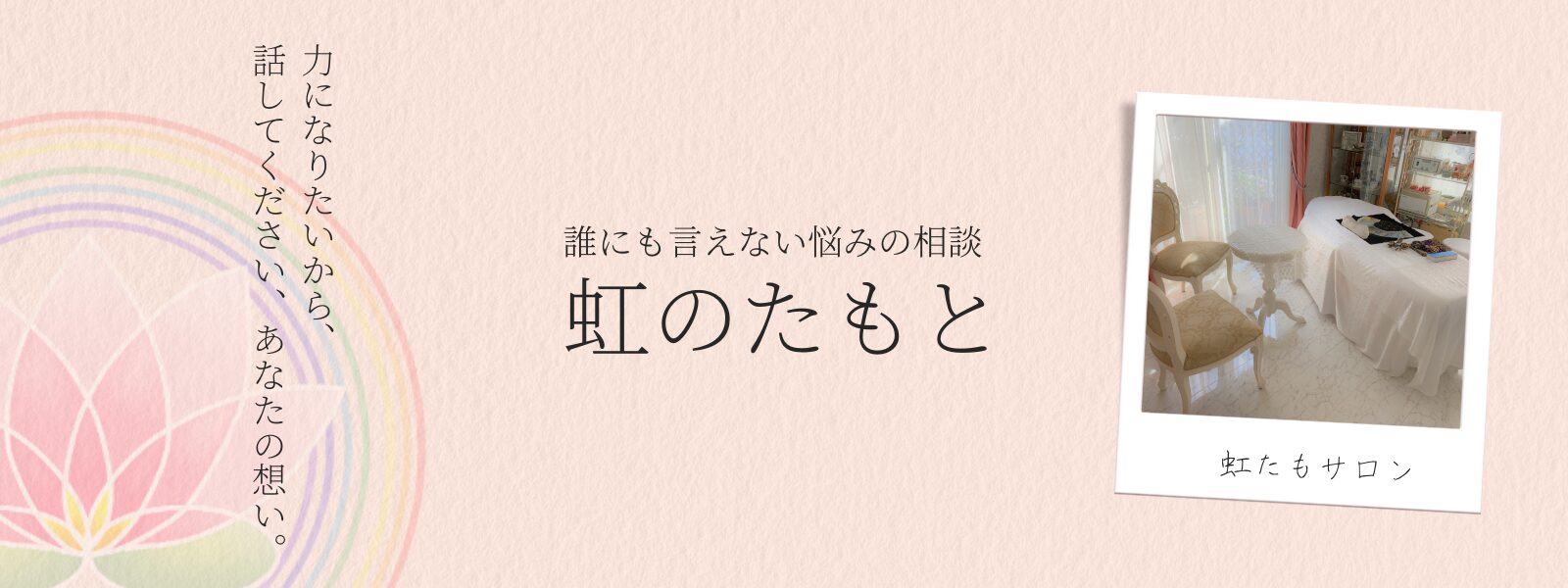


コメント